2022年生産緑地問題というものがあります。
生産緑地問題とは、「生産緑地としてこれまで税制優遇されてきた都市部の農地・緑地が、30年の維持期限を迎え、大量に売りに出されることにより、不動産価格が暴落するだろう」と言われているものです。
調べてみると、不動産価格が暴落するという予想のもとにコラムを書いたり、動画配信している方が結構いらっしゃいました。
都市部のやや郊外に、土地や不動産を既にお持ちの方や、これから物件購入をお考えの方にとっては気になる情報かも知れません。
しかしながら私は、影響が全く無いとまでは断言できませんが、地域差もあり限定的だろうと考えています。
少なくとも、東京23区などワンルームマンション投資対象エリアへの影響はほとんど無いと言えそうです。
このコラムでわかること
1.生産緑地とは
- ・生産緑地制度
- ・税金での優遇が最大の特徴
2.生産緑地問題とは
- ・生産緑地問題の概要
3.不動産価格に影響する?
4.生産緑地問題は限定的。3つの理由。
5.まとめ
1.生産緑地とは
生産緑地制度
生産緑地とは、市街化区域内の農地のうち、生産緑地法で指定された土地のことを指します。
- ・良好な都市環境の確保につながる
- ・公共施設等(公園など)の敷地として適していること
- ・農林漁業の継続が可能であること
- ・500㎡以上(2017年改正で300㎡以上)の規模であること
などの要件を満たすと生産緑地として指定されます。
現在では、全国に12,209ヘクタール(令和元年)の農地が生産緑地として指定されており、そのほとんどは特に東京都、大阪府、愛知県とその近郊の3県に集中しています。西日本は指定が無い県も多く、福岡県ですら僅か2.1ヘクタールです。
気になる方は、ご自身の自治体を調べてみてください。東京都市部だと八王子・立川・町田が多く、区部だと練馬・世田谷といった、住宅地に多いのが特徴です。各自治体のHPで指定されている場所の地図を確認する事が出来ます。
税金の優遇が最大の特徴
生産緑地に指定されると、税制面での優遇が受けられる点が最大の特徴と言えるでしょう。
住宅街の中で見かける農地は勿体ないなぁと思っていましたが、生産緑地に指定され、税金がほとんどかかっていないのかも知れません。
例えば、固定資産税は一般農地並みの課税評価額で計算されるため、大幅に節税することができます。市街化区域内での農地の固定資産税と比べると100分の1まで税金を抑えることが出来るとされており、かなりの優遇制度です。
また、相続時にも納税猶予の制度が有りかなり優遇されます。しかし、営農義務を果たさないと、相続時までさかのぼって相続税が課税されるとともに、猶予期間に応じた利子税まで支払わねばなりません。
2.生産緑地問題とは
生産緑地問題の概要
生産緑地は全体の8割が1992年に指定されているため、指定の日から30年の営農義務が終える2022年に一斉に生産緑地の指定解除がなされることになります。
生産緑地に指定されている間は土地を維持しなければなりませんでしたが、30年経過後は市町村に対して買取の申し出をすることが可能になります。
結果として、市場に大量の土地が供給され、地価の下落を引き起こすことが懸念されているのです。
「東京ドーム〇〇〇〇個分の土地解放!」
みたいな表現を目にすると、インパクトはあるように感じます。
しかしながら、国や各自治体も何もしていない訳では無く、様々な対策をしております。特定生産緑地制度という、10年毎の延長など要件を緩和して生産緑地を継続しやすい環境を整えております。
既に特定生産緑地へと移行している生産緑地も多く、これも各自治体のHPで確認することが出来ます。
3.不動産価格に影響する?
生産緑地が市場に流入することで本当に不動産価格に影響するのか、データを調べてみました。
国交省がまとめている「土地白書」というものがあります。
全国の宅地供給量の推移をみると、平成30年度の宅地供給量は5,967ヘクタール(平成28年度比6.3%増)となっており、近年は6,000ヘクタール前後で推移になります。
また、平成30年の国土面積のうち、住宅地・工業用地等の宅地の面積は、前年(平成29年)の約195万ヘクタールから約196万ヘクタールへと1万ヘクタールも増加しています。
段々と宅地開発の件数や面積は減っているようですが、それでも毎年かなりの面積の宅地が新たに供給されております。年間の土地売買面積は、約15万ヘクタールもあります。
生産緑地は全体で1.2万ヘクタールですから、仮にその半分が土地売買市場に出てきた所で、それほどのインパクトを与えるとは考えられません。
結局はほとんどのエリアは影響を受けないと言えそうです。
4.生産緑地問題は限定的。その理由3つ。
生産緑地問題は、限定的な問題です。注意するべき問題となる対象者は限られるでしょう。
具体的には、当事者、生産緑地地区のアパート経営者、生産緑地が多い郊外に住居を購入予定やマイホームを所有している方でしょうか。
東京23区でワンルームマンション投資を行う投資家にとっては、価格への影響は僅かと言えるでしょう。リスクとして評価しなくても大丈夫そうです。
その理由は3つです。
①特定生産緑地への移行が多い
②アンケート結果も継続が多い
③生産緑地の場所は駅から遠く、相場への影響が少ない
① 特定生産緑地への移行が多い
練馬区の場合、「令和2年11月に405地区、約106.76ヘクタールを特定生産緑地に指定しました」と記載されており、半数以上の農家が既に特定生産緑地へと移行しております。
今度も駆け込みを含め移行する面積は増えていくことが予想され、各自治体で進捗状況の差はありますが、同様に移行が進むものと思われます。
② アンケート結果も継続が多い
国や各自治体で生産緑地を所有する農家にアンケートを取ったところ、2022年以降も生産緑地を8割程維持する予定という結果になっております。
千葉県柏市など各自治体でもアンケートを取っていますが、5割以上は維持という結果になっております。これも各自治体で確認してみてください。
③ 生産緑地の場所は駅から遠く、相場への影響が少ない
生産緑地は駅から離れている場所が多く、相場や不動産投資に影響するような立地ではないという場合がほとんどです。そのため、仮に不動産投資への影響を考慮するとしても個別物件毎に評価するだけで十分と言えます。
では、ワンルームマンションも多い練馬区の場合はどうでしょうか。
練馬区の事例でいうと、生産緑地が多いのは大泉学園町や大泉など、区内でも珍しい鉄道空白地域となっているエリアです。バス利用など交通の便が凄く良いわけではありませんが、鉄道の延伸計画もあり子育て世代が増えているそうです。
生産緑地所有者も当然その計画を意識しているかと思いますので、農地が宅地化するするスピードも緩やかになりますし、鉄道計画次第でエリアの不動産相場は値上がりするでしょう。
以上、市場に出てくる生産緑地は限られている上に、郊外エリアになるため、大きな問題となる可能性は低いと言えます。
5.まとめ
生産緑地による不動産投資の市場への影響は大きくありません。東京の駅近など好立地な物件への投資になるワンルームマンション投資には影響はないと言って良いでしょう。
ただし、個別のエリアによっては相場に影響を与えるかと思いますので、アパート投資をしてみたい方や郊外のマイホームを購入する予定の方は注意が必要でしょう。
結局は、不動産投資をする際に大事なのは立地になります。建物は良くすることは出来ますが、立地は良くすることが出来ません。
投資対象物件の立地がどういう状況かということは、自ら適切に把握していなければ成りません。出来れば現地に行って、最寄り駅から歩いてみることをお勧めいたしますが、無理でもグーグルのストリートビューやマップで確認してみてください。
周辺マップで農地が多いと思ったら、生産緑地というワードを思い出してみてください。そして、自分で評価が出来ない場合はファイナンシャルプランナーなど不動産業者以外のプロに相談してみましょう。
生産緑地問題、コロナの影響やオリンピック後など、不動産においても様々なテーマで情報発信がされており、心配される方もいるかも知れません。
今回は、生産緑地問題について調べてみた結果、行政の対策が適切でよかったと感じました。政策面で上手く誘導出来た事例と言えるでしょう。
それだけ、農業政策や食糧問題が深刻って事でしょうか・・
不動産価格への影響で言えば、空き家問題の方が今後より大きくなってくると思います。
こちらも行政の方で施策を練って対処してもらいたいですね。期待してます。
今回は生産緑地について分析してみましたが、結果的にどうなるかは2022年以降になってみないと分かりません。
私としては、どちらかと言うと景気の動向の方が心配ですが、不動産の良いところは安定感です。その安定感を忘れて小さな情報や損得に支配されないようにしてください。
時間を味方に付けるのが不動産投資です。確かに安い価格で手に入れる事は大事ですが、今始めて成功することが出来るのであれば、始めてしまった方が良いと思います。
今後も〇〇問題でためらう内にあなたの老後が迫ってきてしまった!という事にならないように、様々な情報を発信して参ります。
何か心配事がございましたら、我々にご相談ください。


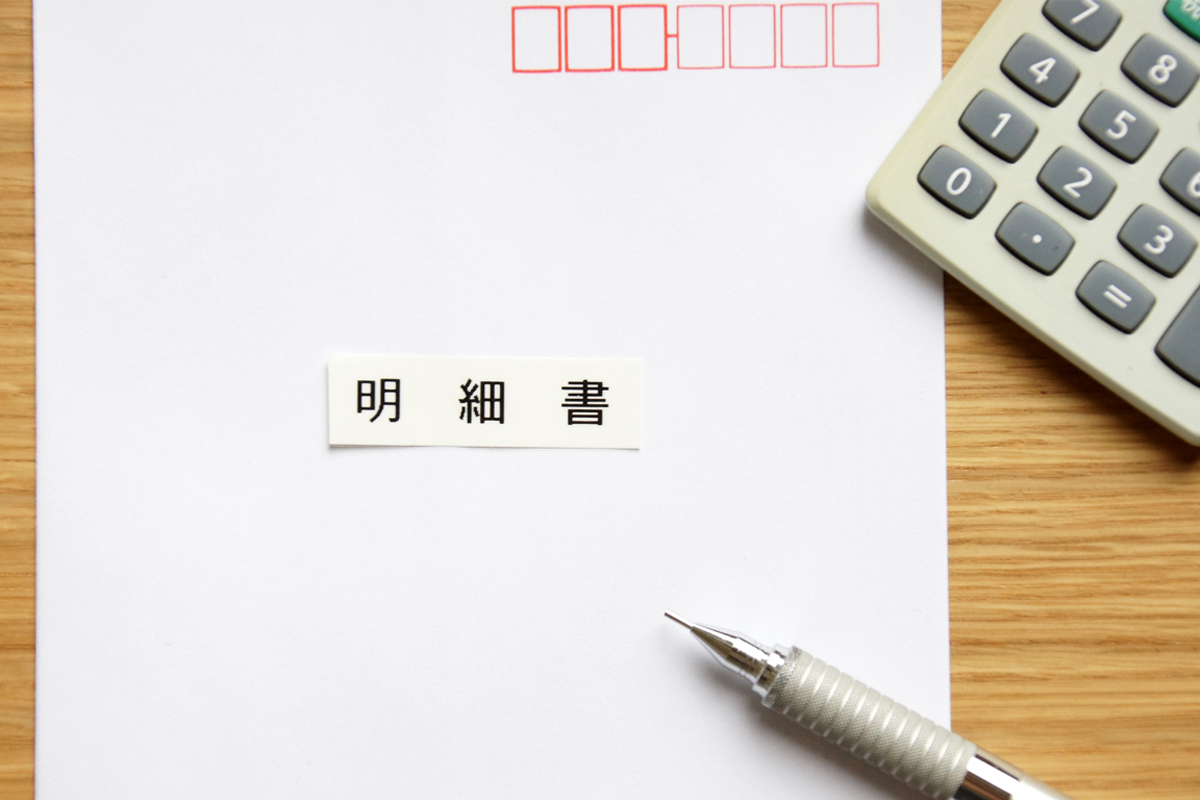


 TOPへ戻る
TOPへ戻る